シリーズ「授業」(令和7年度)
豊かな心と実践力を育み、未来を拓く家庭科教育 ~ともに生きる生活者の育成をめざして~
Ⅰ.研究主題設定の理由
三重県小学校家庭科教育研究会では「現在の高校生は、小学校2年間・中学校3年間の家庭科の学習をいかに捉え、今を生きているのか」という疑問を出発点に、県内の高校生732人にアンケートを実施した。結果、「食」については役立っているが、生活の中で力を発揮できているわけではないことが分かった。また、様々な人や価値観に出会い、学んだ知識・技能をブラッシュアップしているかについては、系統的な学びそのものも含め、検証すべきと考える。「生活の質(Quality of Life)」を向上させるとともに、予測困難な時代を生き、現実的な諸課題に対応しながら仲間とともに乗り越えていける子どもを育てる必要があると考えた。
Ⅱ.めざす児童像
Ⅲ.授業実践
1.題材名 第6学年
「思いを形にして生活を豊かに」
2.研究との関わり
【視点1】子どもの系統的な学びを支える指導計画
高校生のアンケートでは「衣」領域の役立ち感が最も低かったことから「衣」領域で子どもたちが「生活に役立つ」と思える授業をめざした。
生活を見つめ、製作の目的・作りたい物を考えることから始め、製作後にしばらく使用してからふり返りをし、今後の製作に活かし、必要に応じて補修をする時間を設定した。
【視点2】個別最適な学びの実現に向けた授業改善
子どもたちの生活は多様化し、“生活を豊かにする” と思うものは子どもによって様々である。そこで、「自分や身近な人の生活を豊かにする物を作ろう」という課題を設定した。
【視点3】家庭や地域との連携・協力
本題材では、必要な材料の入手方法について保護者への依頼文書を作成し、家族に相談して揃えたり、安価で入手できる店へ行ったりするなど、それぞれの方法がとれるようにした。
3.指導にあたって
本題材では、三重県小学校家庭科教育研究会が授業を通してめざしていきたい子どもをより具体的にとらえられるようにまとめた「ええとこ三重」のキャッチフレーズに沿って、学びを進めた。



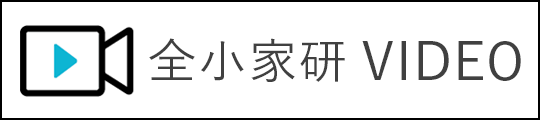
三重県小学校家庭科教育研究会
市立芸濃小学校の実践例を通して